�@�@�@�@�ڎ����@�@�@�����u�c���v�O�҂ցA�@�@��҂ց@�@ �����u������āv��

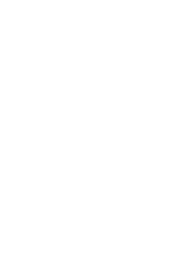 �@�@�@�@�@�Ɏ��I�����{�[�_
�@�@�@�@�@�Ɏ��I�����{�[�_
��i�̒��ɒǂ�����t�̋O�Ձ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�{��N�q
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@
�@�W�����E�j�R���E�A���`���[���E�����{�[�A�P�X���I�̃t�����X���̐��E��
�a���̂悤�ɋ삯���������N���l�ł���B
�@�ނ��u���҂̎��@�v�ƌĂ��Ǝ��̎��@��҂ݏo�����̂́A�P�W�V�P�N�T
���A�P�V�̎��ł���B
�@�ܘ_�A���n�Ȕނ́A����܂łɁA�w�Z�̉ۑ�ő����̃��e����C����������
�Ă���A�����̑啔���͊w���ňꓙ�܂��l�����A���e���ꎍ�̃A�J�f�~�[�E
�R���N�[���ł��ꓙ�܂�����Ă���B�����ĂP�W�U�X�N����̓t�����X��̎�
�����X�ɏ����n�߁A���̂����̈�A�u�ǎ������̂��N�ʁv���u�݂�Ȃ̂���
�̎G���v���ɓ��e���āA����́A�����̎蒼���͗v�����ꂽ���̂́A�P�W�V�O
�N�̐V�N���Ɍf�ڂ���A�l�X�̖ڂ������点���B
�@�����ނ́A�u���҂̎��@�v��҂ݏo���Ă����́A����܂łɏ����A������
�l����^������i�̉��l�����Ƃ��Ƃ��ے肷��B�ނ͂���珉�����т�
�����Q�Q�҂��A�w�Z�̐搶�ł��莍�l�ł��������|�[���E�h���j�[�ɁA���炭
�o�łɏ��͂��Ă��炨���Ƃ������S�������āA�������ēn���Ă������̂����A
�ވ��Ɂu���҂̎��@�v��������莆�̎��̎莆�̖�����
�u�Ă��ĉ������B�l�������]�ނ̂ł��B�����Ėl�͋M�������l�̈ӎu�Ɠ��l
�ɖl�̈ӎu�d���ĉ����邱�ƂƐM���Ă��܂��B�h�D�G�؍݂̐܂ɋ�����
�����l���M���ɂ��n�����Ă��܂���������؏Ă��Ă��܂��ĉ������v
�Əq�ׂĂ���B�K���h���j�[�͂��̗��݂����s���Ȃ������̂ŁA������X�͂�
����ǂނ��Ƃ��o����̂����A���̈ꕶ�́u���҂̎��@�v���ނ�����܂ł�
���������Ƃ͑S�����e��Ȃ����̂ł���A�ނ�����݂̂�^���̎��@�ƍl����
�������ƁA�����Ă��ꂪ�����̃t�����X���̗���Ƃ͂������ꂽ���̂ł�����
���Ƃ�@���Ɏ����Ă���B
�@����ł͈�́u���҂̎��@�v�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł������̂��낤���H�ނ�
���̎��@�ɂ��āA���n�V���������B���̍������w�̏C���w�̎Ⴂ���t�A�W��
���W���E�C�U���o�[���ƃh���j�[�Ɉ��Ă���ʂ̎莆�̒��Ō���Ă��邪�A�T
���P�R���ɏ����ꂽ�C�U���o�[�����̕��́A�Z���A�����{�[���g�̒��ł��̎�
�@���܂��������ł��邱�Ƃ������悤�ɐ��������Ȃ�����ɂ����B����A�Q��
��ɏ����ꂽ�h���j�[���Ă̂��̂́A���Ȃ蒷���A�����������������ď�����
���悤�ŁA�����͐����I�ȕ���������B�]���āA���̎��@�𗝉����邽�߂ɂ�
�Q�ʂ��ēǂނ��Ƃ��K�v�ł���B
�@�����Ŕނ͎n�߂āA�����͎��l�ɂȂ�̂��Ƃ������ӂ������A�����Ă��̂�
�߂ɂ͌��҂ɂȂ�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Əq�ׂĂ���B
�u�l�͎��l�ɂȂ肽���̂ł��A�����Ď��������҂ɂ��邽�߂ɓw�߂Ă��܂��v�B
�ł͌��ҁA���H���C�A���Ƃ͈�̂ǂ�Ȑl�Ԃ̂��Ƃ������̂ł��낤���H��
��́A�ꌾ�ł����A���l�I�ȁA���S�ȔF���͂������A�ʏ�̐l�Ԃ̖ڂɂ�
�����Ȃ����m�̕�������\�͂����l�Ԃł���B�����I�Ȑ��サ���F����ρA
�R�M�g�ɂ���Ăł͂Ȃ��A��ς�ʂ���������S�I�ɔF�����邱�Ƃ̏o����
�l�Ԃł���B�ނ̓C�U���o�[�����Ă̎莆�̒��ŁA
�u���ǐ搶�͂������̌����̒��ɁA��ϓI�Ȏ��������Ă�������Ⴂ�܂���B
�E �E�E�E�E�E�l�́A���̓��ɂ��A�搶�̌����̒��ɋq�ϓI�Ȏ�������
���Ƃ����҂��Ă��܂��B�l�͂����搶�����g�����^���ɔq�ǂ����Ă�
����������ł��v
�u�����V���ڂꂽ�n���҂���������ɂ��Č�����Ӗ��������o���Ȃ�����
�Ƃ��Ă��A�l�����́A�����̐̂��玩�����Ƃł���Ǝ咣���ẮA�Ж�
�̒m���̎Y����ςݏd�˂ė����A�����̉��S�����̊[��������|���Ď�
�Ă�K�v���Ȃ��ł��傤�v
�Ə����Ă���B�����A�ʏ�̐l�Ԃ��s���Ă���m���ɂ��F�����A��ϓI��
�s���S�Ȃ��́i�Жڂ̒m�������������{�[���g�����h���ƂɁA�ǂ�قǏd��
��u���Ă��������l����ƁA�g�Жڂ��h�Ƃ������t�̎��Ӗ��̑傫���͑�
��m��Ȃ��j�Ƃ��Ĕے肵���̂ł���B
�@�@����ł͔ނ������A���m�̕������邽�߂ɕK�v�Ȋ��S�ȔF���͂Ƃ͂�
�̂悤�ɂ���Ύ�ɓ���邱�Ƃ��o����̂ł��낤���H�ނ́A
�u�S���o�̍����ɂ���āA���m�̕��ɂ��ǂ蒅�����Ƃ��K�v�Ȃ̂ł��v
�u���l�́A�����A�傪����Ȃ����ė��_�I���Â��̂���A�S���o�̍����ɂ��
�āA��������҂Ƃ���̂ł��v
�u����͕M��ɐs�����ʋꂵ�݂ł����āA�h�邪�ʐM�O�A���l�I�ȋ���ȗ͂�
�K�v�Ƃ��܂��B�����Ĕނ́A�N�ɂ�����̑�ȕa�ҁA�̑�ȍ߂тƁA�̑��
����l�A�����Ď����̊w�҂ƂȂ�̂ł��B���̂Ȃ�ނ͖��m�̕��ɓ��B��
�邩��ł��v
�Ə����Ă���B
�@���̖��m�̕��������w�����ɂ��ẮA�_���������Ƃ���ł��邪�A���́A
����͌��o�ł͂Ȃ��A�F���Ɍ����ɑ��݂��邪�A�ʏ�̐l�Ԃ̔\�͂ł͌��邱
�Ƃ��o���Ȃ����̂��Ƃł���Ǝv�������B�Ȃ��Ȃ玍�l�͂��̂�����ɂ�����
���Ă��邩��ł���B
�u�ނ͖��m�ɓ��B���܂��B�����ċ������āA���Ɍ�������m�I�ɔF�������
�������Ă��܂������A�ނ͂����������̂ł��B���̔��̑����ŁA�O�㖢
���́A���t���悤���Ȃ��F�X�ȕ���ڂɂ��āA�ނ�������Ȃ炭�����
���B�����Ȃ�Α��̋���ׂ������肽��������ė���ł��傤�B�ނ�͑���
�҂��|�ꂽ�n��������n�߂邱�Ƃł��傤�v
�����A���̖��m�̕��́A���o�̂悤�ɔނ����Ɍ�����̂ł͂Ȃ��āA�ނ̒�
��������@�ɑ����ďC�s��ςҁi���̋���ׂ�������j�Ȃ�N�ł����邱
�Ƃ��o������ݕ��Ȃ̂ł���B
�@���ɔނ́A�G��Ƃ����y�Ƃ�����i�ł͂Ȃ��A���ɂ���Ă�����ʂ���邱
�Ƃ�I�҂Ƃ��ē��R�A����\���̖��ɂ��Č��B
�u�ނ͎������������������A���������A�G�ꂳ���A�����������Ȃ��Ă͂Ȃ��
���̂ł��B�����ނ��ޕ����玝���A�������Ɍ`������A�`��^���A�`����
����Ό`������^���܂��B��������o�����Ƃł��v�B
�u���̌���͍����獰�ւƒʂ��A������A�����A�F���A�S�Ă�v�A�v�l��
�߂炦������v�l���琶�܂����̂ł���܂��傤�v
���m�̕��𐳊m�Ɏʂ���邽�߂ɂ́A���R�̂��ƂȂ�����m�̌�����g����
�Ƃ͏o���Ȃ��B����ł͊��m�̕��Ƃ��Ă����`���Ȃ�����ł���B�܂肱
���ł��܂��A���l�͋L���Ƃ��Đl�Ԃɓ��݂��錾���ς�ے肵�A�����j��
���āA���m�̕����̂��̂ł���悤�Ȍ�������悤�Ƃ����̂ł���B�m��
�ɂ��F����ے肵���Ɠ��l�ɁA���x�͒m������ʌ����n��グ�悤�Ƃ�
���̂ł���B�ǂ��l���Ă��s�\�Ȋ�Ăł���B�����ނ͂��̑�ς����A�ʂ�
�F�l�Ɉ��Ă��莆�̒��ł�������Ă���B
�u���Ƃ�����Ƃ��B�l�̓��̒��ɂ���S�Ă�ł��A�S�Ă���������Ȃ���
�Ȃ�Ȃ��I�����I�n�̉ʂĂ̐l�ڂɂ��ʋ������Ɏ̂Ă��A����s����
�����Ɉ�Ă��A���t������Ƒ��ɂ���Ă����Ȃ�v�z���@�����܂ꂸ�A��
�܂ꂽ�܂܂̏�ԂŁA�����ɂ������ꂸ�A��`���m�����������ɐ��l�̔N��
�ɒB�����q�ǂ��͍K�����B
�\�\�\���̂Ȃ�A��X���������܂ꂽ���Ƃ͑S�Ē��Ԃɉ߂��Ȃ��̂�����I
�\�\�\�����Ď��R�ł��肽���A�S�Ă��玩�R�ł��肽���I�v
�@����]�_�Ƃ́A�u���҂̎��@�v�Ƃ����A�v�ҍ�p�����邱�Ƃɂ���Ď���
�̐^�̎p��߂炦�悤�Ƃ����Ăƌ���Ƃ����f�ނ��A�{���I�ɑ��e��Ȃ���
�̂ł��邱�Ƃ��w�E���A��������Ă���B
�u�����{�[�́A���l�ƌ����҂Ƃ�S����ʂ��悤�Ƃ��Ȃ������悤����������
�炭�ނ��������ׂ��ł������悤�ɂ������������Č���Ƃ��������̑̌n�I
�ȊJ��A�ے������グ�邽�߂̓w�͂́A�ނ̓��ł́A�^���y�ѐi�ނׂ���
�̒T���ƍ�������Ă����悤�Ɏv����v�B
�@��ɔނ͗F�l�̉e���������āA�ʐ^�≹�y�Ƃ����\����i�ɂ������������A
���Ȃ��Ƃ����̎��_�ł́A����\���҂̓���I�̂������B
�@�����Ď����̌f���闝�z�Ɍ�������簐i���A���A����A��H�A����ʂ��ƁA
�����Ԃ̕��s�A�X�ɂ̓��F�����[�k�Ƃ̓������Ƃ��������@�ŁA�S���o������
�����Ȃ��玍��ɗ�ށB���̏W�听�Ƃ����ׂ����̂��L���ȁu�����ǂ�D�v��
����B
���̎��̒��ŁA�����{�[�͎����D�g�l�v����������A�ǂ₢���肩�����
�����ꂽ�D�ɚg���A�D�͊C�̗̐��ɂ���đS�Ă̋L���������āA�^��
���R���l�����A�V�ƊC���D�萬���s��Ȑ��E�ɏ��o���čs���B���l��
�u�l�͐l�������Ǝv�������̂������v
�u�l�͒m���Ă���v
�u�l�͌����v
�u�l�͌��ǂ����v
�u�l�͓˂����������v
�Ɗ�Ă̐������ւ炩�ɍ����Ȃ���A�ʏ�̐l�Ԃɂ͌����Ȃ����A�ނ̖ڂɂ�
������厩�R�̉��ɐ��ގ��ݕ����ʂ�����Ă����A�Y��Ȑ��E���J��L�����
��B
�@�Ƃ��낪�A���炭�̍q�C�̌�ɁA�D�͓ˑR���[���b�p�ւ̋��D���o����B
�u�l�͌Â����ǂ̗������ԃ��[���b�p���������ށv
�����āu���҂̎��@�v�̌��͂ɂ��Ă̋^����������B
�u���O������A�g����߂Ă���̂́A���̒�Ȃ��̈ł̒��Ȃ̂��A�S���H��
���F�̒�������A�����A�����̐��C��v
����ɑ����Ō�̎O�߂́A���̔F�����@�ƌ��������قǔے肵�A��������
������ꂽ�����Ă����̋����[���b�p�Ɨc�N����ւ̋��D�ƁA���D����������
�͂����Ȃ������ɑ���s�k���Ƃ�\�����Ă���B
�u�����A�{���ɁA�l�͂��܂�ɂ��������I�ł͋���������B
�@�S�Ă̌��͍����炵���S�Ă̑��z�͋ꂢ�F
�@�h�X���������l�̐S�𐌂��s�ꂽ���C�͂ň�t�ɂ����B
�@�����@�l�̗�����ӂ��U��I�����@�C�̒�ɒ���ł��܂������̂��I
�@�����l�����[���b�p�̐���]�ނȂ�A�����
�@�����킵���[��ꎞ�ɁA�߂��݂ɖ������ꂤ�����܂���
�@��l�̏��N���A�܌��̒��̂悤�ɂ��낢�M�����
�@�����₽��������
�@�l�͂����A�����@�g��A���O�����̌��ӂɐZ����A
�@�Ȃ��^�ԑD�̍q�Ղ�ǂ��Đi�ނ��Ƃ��A
�@�͑D�̊��Ⓑ����遂���т��Đi�ނ��Ƃ�
�@���l�D�̋��낵���ڂ̉��𑆂��i�ނ��Ƃ��o���Ȃ��̂��v
�@�����m�̕��͑����͂Ȃ��Ǝv�����A���{�ɂP�X�S�O�N��̌㔼�Ɏ��������A
�P�V�ŕ��Ŏ��E�𐋂������q�Ƃ������l������B�ޏ��́A�����{�[��
�u�j�̒��̒j�v�Ə̂��A�\��Łu��\�̃G�`���[�h�v�Ƃ�����e�W���c
���āA�����鋖�e��r���ď��������A�l�����|�p�Ƃ��邽�߂ɏ������E��
�Ƃ������l�������O�̍�i��ʂ��āA�����{�[��m�苭���䂩�ꂽ�B���̒���
���q�̈�e�W�u�F�掄��������Ƃāv�̒���
�u�����͂��̎���A���̊��̒��ɂ��̂悤�ɐ����ė����Ƃ��������̌��̂�
�ׂĂ����̏h���ł���E�E�E�E�E�E�v
�Ƃ������t������B
���サ�������̔F�����@��ے肵�A�����̌�����ے肵�A�C�̗̐��ɂ��
�č��܂łɐA������ꂽ�S�Ă̋L���������A�ӋC�g�X�Əo�������D�́A
�����Ń��[���b�p�Ƃ�������̓��ɑ������h���ɂԂ����������̂ł���B����
�ďh���ɑ���Ȃ̖��͂������B
�@�l�͐t����ɂ͓��Ă��āA�������g�y�юЉ�̌����ɍ������ʉ���ȗ��z
��������̂ł��邪�A����͕K�����܂Ɏ���B�����č��A�����ɂ��錻���̎�
����ے肵�A���̂��������͌����Ĕے肷�邱�Ƃ̏o���Ȃ������Ƃ�������
��ے肵�悤�Ƃ������āA��Y���邱�ƂɂȂ�B���邢�͏h���ɔ��t���邽��
�ɁA��L�̎��l�����̂悤�ɁA����Ȃ鎀��I�ԁB�t�Ƃ����̂́A������
�l�X�ɂƂ��Ă͐��ɋꂵ�����̂Ȃ̂��B
�@�l�Ԃɂ͒B���s�\�ȗ��z������������{�[�ɂƂ��Ă��A�t�͑傫�Ȋ�@
���͂���̂������B�ނ͂ǂ��������Ă��h�����瓦��邱�Ƃ̏o���Ȃ���
�������������ށB�u�p�v�Ƃ������͂����@���ɕ\�킵�Ă���B
�u���̔]���A�����Đ��Ŏ�����
�@�����ς��ʓ��C��f�����̉ו�
�@�������i�C�t��
�@�����Ă��܂�Ȃ�����́A
�i�����A�z�߁A�@���A�O���A�������A
�@�������炸�Ȃ�܂��I
�@�����ė������̂Ă��Ȃ�܂��I
�@�����@�f���炵���I�j
�@����A�ʖڂ��G�{���ɖl�͎v��
�@���̓i�C�t�ł�����
�@�e���͐ΑŌY��
�@���͉��t���
�@�������ĕЕt���Ă��܂�Ȃ������
�@���҂̂��̎q�ǂ��A�����������Ȃ��킯�ҁA
�@�����͈�u����Ƃ�
�@���܂����◠����~�߂͂��Ȃ����낤�A
�@���b�L�[�R���̔L�̂悤��
�@���鏊���L������I
�@�ł��A�����@�_�l�I���������ʎ��ɂ�
�@�ǂ����ŋF��̐���������܂��悤�ɁI
�@���̎���A�����{�[�͌���C�����W�ƌĂ�����̎����������A�����
�̒��ɂ������ɁA���܂̋�Y������Ă���B
�@�Ⴆ�u�����̊쌀�v
�@�u�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�@��������
�@�@�@�@�@�@�킵��͂��O�̂������������I
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����c�l����I
�@�@�@�@�@�@���̌��Ƒ��̗�
�@�@�@�@�@�@�₽�����ɂ��������G��āB
�@�@�@�@�@�@�킵��̐h�����C���ɂႱ�������������B
�@�@�@�@�@�@���܂����̂Ȃ����z�̌��𗁂т�
�@�@�@�@�@�@�l�Ԃɂ͉����v��H�ۂނ��Ƃ��B
�@�@�l�\�\�\�ؒn�̉͂Ŏ��ʂ��Ƃ��B
�E �E�E�E�E�E
�@�@�l�\�\�\�����A�����A�����̐��炩�Ȉ��ݕ��A
�@�@�@�@�@�@�R�b�v�ɂ��������ɍ炭�ԂȂǁG
�@�@�@�@�@�@�`�����G�p��
�@�@�@�@�@�@�l�̊�����������Ⴍ��Ȃ��B�v
�@���������Ƃ́A����܂ł̐����̌��̑S�Ă�ʂ��ă����{�[���K�肵�A���R
�ɂȂ肽���Ƃ�����]�̎����������Ȃ����j�A�`���A�����A�����ĉƒ�I�܂�
�Љ�I���̂��Ƃł���B���������́A���������̎��ɂ͂���������ƌ�����
��������l�Ɋ��߂邪�A�ނ͍ő��A�`���I�ɔ������Ƃ���Ă�����̂ɂ͌���
���������A�������������ꂽ�ؒn�Ŏ��ʂ��Ƃ����l���Ă��Ȃ��B
�@�ނ͂���Ȏ����̐S���u�l�̐S��v�Ƃ������̒��ł����\������B
�u�l�����ɂƂ��āA����������ʂɊg����A
�@��s�E���s���A�{��̋��т����������A
�@�S�Ă̒������n���̒�̂����苃�����������G
�@���Ȃ��p�Ђ̏��k����̗����n��l�̐S���Ȃƌ����̂��v
���̎��͈�ʓI�ɂ́A�p���E�R�~���[�k�̉�ł̌�̃u���W�����W�[�̊���
�Ԃ��ɑ���{���\���������̂ł���Ƃ���Ă��邪�A���l�̐S�݂̍�悤
���S�������̂ƕ߂炦�Ă����܂�Ȃ����낤�B
�@�����Đ�]������ė���B�ނ͂�����u�L���v�Ƃ������̒��Ŏ����̂悤��
�\������B
�u�l�͉A�T�Ȃ��̐��̖ڂ̂�������
�@�����@�����ʏ��D�A�����@�Z������r�I�l�ɂ͓E�߂Ȃ��A
�@���̉Ԃ��A���̉Ԃ��A�l��Y�܂����F���Ԃ�
�@�D�̐F�������ɂ悭�������Ԃ��v�@
�@�Ԃ͖��m�̕��̎�����\�����߂ɁA�����{�[���悭�g�����t�ł���B�]����
���ꂪ�E�߂Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�u���҂̎��@�v�̍��܂�[�I�Ɍ�������̂ƍl
���ėǂ����낤�B
�@�ނ͎������A���z�Ƃ����ϓ_����ق��A�����l�Ȏ҂Ɣ��肵�āA���R����I
�Ԃ��Ƃ��l����B
�u�������R��A�l�͖{���ɂ��O�̎�ɂ������Ď��ɂ����B
�\�\�\�����@����ȂɌǓƂłȂ��A����Ȃɖ����l�Ȏ҂Ƃ��Ăł͂Ȃ�
�������v
�@�����ނ͎��疽��f���Ƃ͂��Ȃ��B���̂����ɁA���̊Ԃł��ꂵ�݂�
�Y��邽�߂ɖY��̏u�ԂƖ�������߂�B
�u��ԍ������̉́v�ł�
�u�����I�@���旈��
�@�S�̔R���鎞�旈���v
�Ƃ������傪��x�J��Ԃ���Ă��邵
�u�T�͖؉A�Łv�ł�
�u�������肽���A�ς�ꂽ���v
�Ƃ��q�ׂĂ���B
�@���l�ŏ����Ƃł����鐴����s�́A�������O�ɂ��Č���������u�C�̓��v
�̒��ŁA�������A�����݊w���Ă����ꍂ�̊w���V���u���ˎ���v�ɓ��e������
�u�C�ɖ�����v�ɐG��A���������E�̘a�炰��ꂽ�Ô��Ȍ`�Əq�ׂĂ��邪�A
�܂��ɂ��̒ʂ�ł���B
�@���̂��̎��_�Ń����{�[�����E�����Ȃ������̂��͒肩�ł͂Ȃ����A���
�u�n���̈�G�߁v�́u�����v�̒���
�u�Ȃ�Ɩl���I�[���h�~�X�̂悤�ɂȂ������Ƃ�A����������E�C�������Ƃ́v
�ƌ���Ă��邱�Ƃ�A�����ƌĂ�Ȃ���A��̉Ƒ����Ă̎莆�ł́A���ʂ�
�ʼn��x���A�������������ʂ����Ă��Ȃ����Ƃ��ǂ�������悢�����k���Ă���
���S������l����ƁA�ĊO��������邪�̂Ɏ��s�o���Ȃ������̂����m��Ȃ�
���A�܂����E���߂Ƃ���J�g���b�N�̋��`�̉e���������������m��Ȃ��B
�@�Ƃ������ނ́u���҂̎��@�v�̊�Ă����܂�������A��Y�ɑς��Đ����i��
���A����̌���C��������������A����̐��_�j�Ƃł������ׂ��u�n���̈�
�G�߁v�������B���̎U�����W���o�ł����܂ł̌o�܋y�сA�ŏI�͂́u���ʁv
�����ɑ��錍�ʂł���̂��A�܂��������U�����W�ł���u�C�����~�i�V�H���v
�Ƃ̑n��N��̊W�ɂ��ẮA���łɑ����̌����҂���������Ă��邱�Ƃ�
���邩��Ȃ����A�ނ���e�Ɂu�����̉^���͂��̖{�ɂ������Ă���v�ƌ�����
�������Ƃ��番��悤�ɁA�����{�[�͎���̐����̖���q���Ă����������
�̂ł���B
�@�X�҂��琬�邱�̎��W�̍ŏ��͖̏͂���ł��邪�A
�u���ẮA�����l�̋L�����m���Ȃ�A�l�̐����͋����ł���A�S�Ă̐l��
�S���J���A���Ƃ�����������Ă����v
�Ǝn�߂��Ă���B����̓G�f���̉��̂��Ƃ������Ă���Ƃ��l�����邪�A
���́A�ނ��u���҂̎��@�v�Ƃ����B���s�\�ȊϔO�I���z�Ɏ��߂����O�́A
�c���̍��̂��Ƃł���Ɠǂ݂����B���̂Ȃ�A�������̌��
�u�����A�ڂ��͔���G�̏�ɍ��点�������������Ă������X�����Ǝv�����B
���\�\�����ēłÂ��Ă�����v
�Ƒ�������ł���B
���Ƃ͂����ł́A���҂̖ڂɉf�関�m�̐��E��\�킵�Ă���ƍl���ėǂ���
�낤�B�܂莍�l�́u���҂̎��@�v�̊�Ă������Ď������K���ɂ�����̂ł�
�Ȃ������Əq�����Ă���̂ł���B�]���Ă��̐��s��ł́A���������傻�ꂽ
���z�Ɏ��߂��ꂽ�҂����R��Y����
�u�l�́A�l�̐��_�̒��ŁA�S�Ă̐l�ԓI��]�����ł�����Ɏ������v
�ƌ���A
�u�s�K���l�̐_�������v
�Ƒ����B�����Ĕނ͓D���̒������ꂵ�݂𖡂킢�A���ɂ�
�u�����ďt���l�ɂ����܂����s���̏����^��ŗ����v
�ƂقƂ�Nj��C�̏�Ԃɂ܂Ŏ��������Ƃ��q�ׂ邾���A����ɑ�������ɂ́A
��̓W�]���_�Ԍ�����B
�u�Ƃ��낪�A�ɂ��ŋ߂̂��Ƃ����A�������Ŋ��̂����̉����グ�����ɂȂ���
����̂ɋC�t���āA�l�͐̂̋����̌���T�����Ǝv�������B�����łȂ狰
�炭�H�~�����߂��邾�낤�ƁB
�@���������̌����B�\�\�\���̎v�����͖l���������Ă������Ƃ𖾂炩�ɂ�
��I�v
�@�̂̋����A�������z�Ɏ��߂����O�̏�Ԃ����߂����߂̌��A����͎�
���������ƌ����̂ł���B�܂�l�Ԃ��K���ɂ���̂́A�����i����̓L���X
�g���̌��t�ł����Đ_�Ɨאl�ɑ��鈤�̂��Ƃ������̂ł��邩��A���炭��
�������͊ϔO�����܂�ł��邾�낤�j�ł���ƋC�t���A�u���҂̎��@�v�̊��
��簐i�������ʍ��܂��A������]�݂����������ɂȂ������Ƃ́A���ł͈ꖕ��
���Ƃ����v���Ȃ��Ƃ������Ƃł���B
�@���ɂ���u�����v�́A�}�������ɂ���āu���_�I�Ɉٍ��̂��̂Ƃ���������
���̂Ȃ������̋P���v�ƌĂꂽ�����{�[���A���サ�������ɂǂ����Ă��K��
�o���Ȃ��Ȃ��A��ؐl�ƒ�`���A���Ƃ����j�̒��Ɉʒu�Â��悤�Ƃ���w�͂�
��������̂ł��邪�A���̕��͂͑S���������������A���ʂɗ������悤�Ƃ���
�Ή��Ƃ�����ł���B����������́A�ނ����_�I�ɋɓx�ɒǂ��l�߂�ꂽ���
�ɂ����āA�S�ɕ����Ԃ��Ƃ����̂܂��X�ɏ������߂Ă��������ʂł��邩��
�ł���A�ǂ�ł���Ɣނ̓������v��������B���������A�{���l�Ԃ̐S��
�͐������ȂǂƂ������̂͂Ȃ��̂��B���̒�����A���̎��_�̗���ɉ�������
���E���Ă݂悤�B
�@�܂��n�߂̕���
�u�����I�N���l�̌��t������قǂ܂łɕs���Ȃ��̂ɂ����̂��H���ꂪ���Ɏ�
��܂ŁA�l�̑ӑĂ��A���قǂɁv
�Ƃ���A�܂��I���̕��ɂ�
�u�l�͂܂����R��m���Ă��邩�H������m���Ă��邩�H�\�\�\�ő����t�͂�
���v
�Ƃ���B����͌���\���ւ̕s�M�̕\���ł����āA���l�A��������\���҂ł�
�邱�Ƃ�I�сA���҂̎莆�̒��Ōւ炩��
�u�ނ͎������������������A���������A�G�ꂳ���A�����������Ȃ��Ă͂Ȃ��
���̂ł��B�����ނ��ޕ����玝���A�������Ɍ`������A�`��^���A�`����
����Ό`������^���܂��B��������o�����Ƃł��v
�ƌ���������{�[�ł����Ă݂�A�����m��ʂقǂ̔s�k���𖡂�������Ƃ�
�낤�B�����A�ނ͂��̏������
�u���т��A���ۂ��A�x�肾�A�x�肾�A�x�肾�A�x�肾�A�E�E�E�E�E�E
�Q�����A�������A���т��A�x�肾�A�x�肾�A�x�肾�A�x�肾�v
�Ɠ����̒��ł̖Y������Ă���B�܂��A���̎��̒��قǂɂ�
�u��ԗǂ��͍̂��l�Ő����s��Ė��邱�Ɓv
�Ƃ������������B�������̂Ƃ���ł�
�u�~�̖�A�h�������A�ߕ����Ȃ��A�p�����Ȃ��X���ɂ���ƁA��̐����l��
�������S����ߕt�����F�w�コ�̌̂������̌̂��F���O�͂����ɂ���F����
�͋������x�v
�ƁA����ł��������тĂ��鎩�����m�肷�錾�t������B�����Č㔼�ɂ�
�u�������l�ɐ��܂ꂽ�B���E�͗ǂ��B�l�͐l�����̂��悤�B�l�͌Z�킽������
�����B����͂����A�q�ǂ��̂���̖Ƃ͈Ⴄ�̂��v
�ƌ����̐l��������A�l�Ԃ��������Ƃ����ӎu��\�����錾�t������B��
���ނ́A�������Q�Ȃ������A���݂Ȃ�ʃG�l���M�[���߂������́A�ǎ��I��
�Љ�l�Ƃ��Đ����悤�Ɩ]��ł��A���̔��e�ɂ͔[�܂��Ȃ����Ƃ�m����
����B�����Ă܂��A����z���B
�u�l�͗ǎ��Ƃ������̓V�g�̒�q�̂Ă���ɐȂ�����Ă���̂��B��������
�̍K���ȂǁA�ƒ�I�Ȃ��̂ł���A�����łȂ����̂ł���A�ʖڂ��A�l�ɂ�
�������B�l�͂��܂�ɕ��������A���܂�Ɏア�B�l���͘J���ɂ���ĉԊJ��
�Ƃ͐̂Ȃ���̐^�����F�������̖l�̐����ɂ͏[���ȏd�݂��Ȃ��B����͕�
���オ��A�l�̐��̂��̑�Ȏx�_�ł���s���́A�͂邩��ɕY���Ă���B
�Ȃ�Ɩl���I�[���h�~�X�̂悤�ɂȂ������Ƃ�A����������E�C�������Ƃ́v
�@�܂胉���{�[�́A���̎��т̒��ł́A�l���̍m��Ɣے�̊Ԃ��s���߂�
���Ă���̂ł���B
�@���ɗ���̂́u�n���̖�v�ł���B���̏͂͑��e�ł́u�U��̉��@�v�Ƃ���
��ɂȂ��Ă���A���ꂪ�����ʂ�A��ɁA�L���X�g���̐M�ɖ߂�ꂵ�݂���
�~��ꂽ���Ƃ�����]�ƁA�c�������e�ɂ���ĐA���t����ꂽ�����̕���
���`�Ɋ�Â����L���X�g���ւ̔����Ƃ̑���������Ă��邪�A���ɂ���ق�
�u���҂̎��@�v���Ȃ݂Ă��镔����������B
�@�Ⴆ�Ζ`���ɒu���ꂽ���s�A
�u�l�͂����Ղ����̓ł����݊������B�\�\�\�l�̎��ɓ͂����������O���яj
������Ƃ����������������Ă����B�ł̌������͖l�̎l����P���Ȃ��A
�l���b�`�ɂ��A�n�ɒ@���̂߂��B�A�������Ď��ɂ������A�����܂�A����
���Ƃ��o���Ȃ��B����͒n�����A�i���̐ӂߋꂾ�I���Ă����A�Ȃ�Ɖ�
�R�������Ă��邱�Ƃ��I�l�͌����ɏĂ�������I�v
�@���̓ł�����\���Ă��邩�ɂ��Ă͏��������邪�A���́u���҂̎��@�v��
��Ă�\���Ă���ƌ������B���̂Ȃ炻�̂������
�u�l�͑P�ƍK���ւ̉��S���_�Ԍ����B�l�Ɏ�����`�����Ƃ��o���邩�A�n����
��C�͎^�̂������Ă���Ȃ��B����͖����̖��f�I�Ȑ����������A�Ô��ȗ�
�I���t�A�͂ƕ��a�A���M�Ȗ�]�A���̑��F�X�������B
���M�Ȗ�]���I
�����Ă�����܂��l���Ȃ̂��B�\�\�\�����@�����n�������i���ɑ����̂�
������I�����̎葫����肽���Ɩ]�ޒj�́A�������n���ɑ��Ă����
�ł͂Ȃ����낤���H�v
�Ƃ��邩��ł���B
�ނɂ͍����̒��Ō����l�X�Ȏ��������t�ɂ��邱�Ƃ��o���Ȃ��B���l�ł���
���Ƃ�������l�ԂɂƂ��ẮA�������̒n���ł���B�����āA���܂�ɂ�
��簂ȗ��z��ǂ��҂́A���z�̒Nj��̖W���ɂȂ�葫�A�������̂�ے肷�邱
�ƂɂȂ�A���̂�ے肵�����邱�Ƃ͒n���ɑ��Ȃ�Ȃ��B
���̏�����ł́A�����{�[�́A���Ă̑�]�u���҂̎��@�v�����}�I�Ɍ��B
�u�����[�����I�E�E�E�����Ś�����鐔�X�̌�T�A���p�A�U��̖F���A�c�t��
���y�B�\�\�\���̏�A�l�͐^����߂炦�Ă���A���`�����Ă���F���S�Œf
�ł��镪�ʂ�����Ă���A�����ɋ߂Â��Ă���ƌ����̂�����E�E�E�v����
���肾��v
�����Č���ɂ��\�����قƂ�ǒf�O�����悤�Ȍ��t������B
�u���o�͐��m�ꂸ����B����͐������l�����ł���ɓ��ꂽ���̂��F�E�E�E
�l�͂���ɂ��Ă͌����������B���l�����⌶���҂��������i���邾�낤
����v
���͐�ɁA�����{�[�����悤�Ƃ����u���m�̕��v�Ƃ́A���o�ł͂Ȃ��A����
�F���̒��Ɏ��݂��邪�A���ʂ̐l�Ԃ̖ڂɂ͌����Ȃ����̂��Ƃł���Ə������B
�����������Ŕނ́u���o�v�Ƃ������t���g���Ă���B����͋��炭�ނ��u���m
�̕��v���ǂ��\��������ǂ������炸�A�����̑��̎��l�����̉e�����Ďg
�������t�ł��낤�B�܂��A�����]�Ƃ́A�����{�[�����邱�Ƃ�]�͉̂F
���̎��ݕ��ł��邪�A������������邽�߂̕��@�����A�������ɗ�������
�ŁA���ʂƂ��ē��邱�Ƃ��o�����̂͌��o�ɉ߂��Ȃ������Ə����Ă���B����
�͔��ɋ����[�����ŁA�Ⴆ�Δނ����K�̍s�҂̂悤�ȏC�s���@���̂��Ă���
�A�F���̎������ς��邱�Ƃ��o���������m��Ȃ��B�����A�V���������B����
���̐}���ق̉{���L�^�ɂ��A�ނ́A������̎��l�A���R���g�E�h�E���[��
�̍�i��ʂ��ăC���h�̓N�w�ɂ��G��Ă����������B
����͂Ƃ�����_�|��߂��ƁA�ނ́u���҂̎��@�v�����}�I�Ɍ��A�قƂ�
�ǒf�O�����悤�ɏq�ׂ���A����ɂ���p�����Ɲ�������B
�u�l�͖��p�����̎x�z�҂��v
�����čŌ�̕��ł́A
�u�����A�܂������ɂ悶�o��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��I�l�������b�`���߂�
�Ȃ�Ȃ��̂��I�����Ă��̓ŁA�������ꂽ���̐ڕ��v
�Ɛ����邱�Ƃ̐h����Q���Ă���B�b�`�Ƃ́A�O�q�̎���̎葫����肽
���Ɩ]�ޒj�̎p�̂��Ƃł��낤�B
�����A���̎��̒��Ń����{�[�́A�Ȃ̑�]�������s�\�Ȃ��̂ƔF�߂Ȃ���
���A���z�̒B����W����h���ɑ��鋑�ۂ��т��ׂɎ���I�Ԃ��Ƃ��o�����A
���܊���������܂ܐ����Ă���B���̈���ł́A�Ȃ�Ƃ������Ɛ܂荇����t
���Ă������Ƃ����ӎu�����ܐ��܂��̂����A���܂����z�ɂ�閣�f�I�Ȑڕ��A
���ꂽ�ڕ��̎x�z���甲����Ȃ��B����ȏ�ԂŐ����Ă������Ƃ̋ꂵ��
������Ă���̂ł���B
���̎��ɗ���̂́u�����v���T�A�u���C�̏����v�ł���A����ɂ́u�n����
�v�v�ƕ��肪���Ă���B���̏����ƕv�������w���Ă���̂��ɂ��ẮA��
�F�����[�k�ƃ����{�[�̂��Ƃł���Ƃ���̂��ʐ��ł��邪�A���́A��ǂ���
�����ɁA�����ł̓����{�[�͓�ɕ��Ă��āA�v�͌ȂɊϔO�I���z���ۂ�
�ҁA�����͒B���s�\�ȊϔO���ۂ���ꂽ���g�̌Ȃ�\���Ă��āA���̎��͂�
�̕������Ȃ̂��߂������̋ꂵ�݂��A���ʂ̐l�ԂƂ��ĎЉ�ɏ������Đ�
���Ă����̂ɁA�v�ɏo��A����������ɁA�ނ̗��z�����L�������A����
�Ɏx�z����āA�����₦�₦�ɂȂ��������̌�����Č�������̂Ƃ������
�����B���������g�������ꂵ�݂̒��Ő����Ă����̂ŁA�����Ɉ�����
�ǂ�ł��܂����̂ł���B����͈ꕔ���������đ��̕������̂ĂĂ��܂�
�����ǂݕ��ł��낤�B�������A�D�ꂽ���w��i�͂ǂ̂悤�ȓǂݕ���������
�����̂ł͂Ȃ����낤���H�]���āA���̍�i���A���̕����ϓ_����̂݉�
�߂��邱�Ƃɂ͑傫�Ȗ��������邱�Ƃ͏d�X���m�̏�ŁA�����āA���̗����
���r���ēǂ�ł����Č��悤�B����ɁA����ɑ����u�����v���U���A���x�͕v
�̌�����āu���҂̎��@�v�̎��H�̌o�܂�����Ă���̂ł��邩��A���̉�
�߂����Ȃ������ł͂Ȃ����낤�B�����A���̂悤�ȗ�����̂��]�Ƃ�����
���킯�ł͂Ȃ��B
���̎��т́A���C�̏������_�Ɏ����̋ꂵ�݂�i����`�ŒԂ��Ă���B
�u�n���̓��A��̍��������ł͂Ȃ����F
�������@���Ȃ�v�A�킪���B���Ȃ��Ɏd���鏗�����̒��ōł��S�߂Ȏ҂�
�������ǂ������܂Ȃ��ʼn������B�킽���͂����ʖڂł��B���肵�Ă���
���B����Ă��܂��B���Ƃ��������ł��傤�I�E�E�E�E�E�E��
�፡�A�킽���́A���̐��̂ǂ��ɂ��܂��I�����@�킽���̗F�l�����I�E�E�E
�������A�F�l�Ȃ�Ă��܂���E�E�E����قǂ̋C�Ⴂ�����A����قǂ̐ӂ�
��͂��܂����đ��݂������Ƃ�����܂���E�E�E���Ɣn���������Ƃł���
���I
�Ⴀ���I�ꂵ���A�킽���͋�������ł��܂��A�{���ɋꂵ���̂ł��B�v
�����A�����ɋꂵ���Ƃ��A��������ϔO�I���z�ɕ߂炦��ꂽ�l�ԂɂƂ�
�āA���̎����������̂͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B�u�n���̕v�v�ɖ������Ă��܂�
���u���C�̏����v�ɂƂ��ẮA�v�̌��t�͑S�Ė��f�I�ɕ�������B
�u�킽���́A�p�J���h���ɁA�c�����𖣗͕ς���ނ̌��t�Ɏ����X���܂��v
�]���Ĕޏ��́u�n���̕v�v�̖ژ_����s�\�Ȃ��Ƃƌ�����
�u�����I���̐l�͈����ł��A�{���ɁA�l�Ԃł͂���܂���v
�Ƃ܂Ō����Ȃ�������̉e�����瓦���ꂸ�A�l�Ԃɗ^����ꂽ���������ۂ��A
�v�̗��z�ɓ��B�����Ȃ�������ڑł������A�Ȃ̓��̂�ے肵�A�[���ƂȂ��
��B
��킽���͒n���̕v�̓z��Ȃ̂ł��A���C�̏��������ɖ��킹�����̕v
�ł��B�H��Ȃ��Ⴀ��܂���A���ł�����܂���B����Ȃ̂ɂ킽����
�v�����ʂ������āA���̐����̂Ă܂����B
�E
�E�E�E�E�E
�@�킽�������ĈȑO�͂ƂĂ��܂Ƃ��ȏ��ł����A�[���ɂȂ�ׂɐ��܂�Ă���
�킯�ł͂���܂���I�E�E�E���̐l�̐_��I�Ȕ��������A�킽���𖣘f����
�̂ł��B�킽���́A���̐l�ɕt���čs�����߂ɐl�ԂƂ��Ă̋`����S�Ă���
�����ɂ��܂����B���Ƃ��������ł��傤�I�{���̐����Ƃ������̂������̂�
���B�킽�������́A���̐��ɐ����Ă��Ȃ��̂ł��B�킽���͔ނ̍s���Ƃ���A
�ǂ��ւł��s���܂��A�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��E�E�E�E�E�E�v
�u���荞���̐l�̂��Ƃ����̘̂e�ŁA�킽���͊�������炸�ɁA�ǂ����
���Ԃ��A�ǂ����Ă��̐l�͂�����������瓦���o���������Ă���̂��낤��
�l���ĉ߂��������Ƃł��傤�B���܂����Ă���Ȋ�]��������l�Ԃ͂���
����B
�킽���̈́������ނ̐g���Ă��Ăł͂Ȃ��̂ł������������̐l�͎Љ�ɂƂ�
�đ傫�Ȋ댯�ɂȂ邾�낤�ƔF�߂Ă��܂����B�v
�@�����A���ہA�����{�[�̉e�������Ə̂���ǂ�قǂ̎�҂������A���}
��������L���Ȍ������������ۂ��A�����ɐ����鐶�g�̎����Ɠ����Ĕs��A��
�]�̕��ɒǂ����܂ꂽ���Ƃ��낤�B�����Ă������Ɏ��疽��f�����҂����Ȃ�
�炸����B
�@���̌�͂��������B
�u���̐l�́A������������A�l����ς���閧�������Ă���̂ł��傤���H��
��A�����T���Ă��邾�����A�Ƃ킽���͎����̍l����ł������܂����B��
���������A���̐l�̎����ɂ͖��@���������Ă��܂����A�����āA�킽���͂�
�̗��ɂȂ��Ă���̂ł��B�E�E�E�E�E�E�v�B
�@�����ɍ������ʗ��z�ɂ́A�l����ς���͂͂Ȃ��B�����̌�����Č�郉
���{�[���g�����̂��ƂɋC�t���n�߂Ă͂���̂����A���܂��S�ɑ����������z
�̖��͂ɕ߂���Ă���̂ŁA�����o���p��m��Ȃ��B�I���߂��ɂȂ��āA
�����́A�͂�����Ǝ����̉߂���F�߂邪�A����ł��A�ǂ������炻�����甲
���o�����Ƃ��o����̂��͕��炸�A���ς�炸�n���̐h�_�����ߑ����Ă���B
�@�u���̊Ô������܂��j�ł������炷���̂ł��B�킽���͂���ɏ]���Ă��܂��B
�\�\�\�����@�킽���͋����Ă���̂ł��v�B
�@�]���Ă��̎��тł́A���l�͊ϔO�I���z�̌��ɋC�t���n�߂Ȃ�����A�܂�
��������E�p�o���Ȃ���ԂŁA�������Ă���̂ł���B
�@���ɂ���̂́u�����v�̇U�A�u���t�̘B���p�v�ł���B����́A�O�q�������A
�n���̕v���A�u���҂̎��@�v�̎��H�̌o�܂���������̂ł���B
�@����͂����n�܂�B�g���Ă��铮���݂͂ȉߋ��`�ł���B
�u���x�͖l�����Ԃ��B�l�̐��X�̋C���������̈�̘b���B
�l�́A�����ƈȑO����A���蓾��S�Ă̕��i�����L���Ă���Ǝ������A�G��
�⌻�㎍�̂��̕�������}���Ă����v�B
�u�l�͑S�Ă̖��p��M���Ă����v�B
�@�����Č��������ʂ���邽�߂ɍs�����A�V��������̔�����ڎw���Ă̍H�v
�����B
�u�l�͕ꉹ�̐F�������I�\�\�\A�͍��AE�͔��AI�͐ԁAO�͐AU�͗B
�\�\�\�l�͂��ꂼ��̎q���̌`�Ɠ������K�肵���A�����āA���̓����A�{
�\�I�ȃ��Y���ł����āA�����銴�o�ɓ��B�ł��錾�������Ǝ�����
�Ă����B�|��͕ۗ������B
�@�@�ŏ��͏K�삾�����B�l�́A���ق��A�ł��������A�\�������ʕ�����������
���B�l�͂߂܂������t�ɗ��߂��v
�@�����Ō���Ă���̂́A�����{�[���ȑO�ɏ������L���ȁu�ꉹ�v�̎���
���Ƃł��邪�A����͌�������̍ŏ��P�ʁA�ꉹ�ɂ܂ŕ������āA�����o��
�p���āA���҂ƂȂ������l�̖ڂɉf���������A��ςɂ���Ęc�߂��ɁA���̂�
�ܓǎ҂ɓ`���悤�Ƃ������݂ł���B�u�|��͕ۗ������v�Ƃ���̂́A���炭
��ɏ������u�C�����~�i�V�I���v�̂��Ƃ��낤�B
�@���̌�ɂ́A�u�����ǂ�D�v����u�n���̈�G�߁v�܂ł̊Ԃɏ����ꂽ�����R
�ґ}������Ă��邪�A���l�͂����ɂ����̎��̉��l��ے肷��B
�u�l�̌��t�̘B���p�̒��ł́A�g���Â��ꂽ���I���ꂪ�傫�Ȉʒu���߂Ă�
���v
�@�����Č��҂̖ڂɉf�����������A�P���Ȍ��o�ƌĂсA�^�ɖ��m�̕��ł͂Ȃ�
�����̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�O��\������B
�u�l�͒P���Ȍ��o�ɂ͊��ꂽ�F�l�͋ɂ߂Ă͂�����ƌ������̂������A�H���
����ꏊ�ɉ̎��@���A�V�g�����ɂ���č��ꂽ���ۂ̊w�Z���A�V�̊X
�����삯��y���l�֔n�Ԃ��A�̒�ɋq�Ԃ��G�����������A�_����G�ʑ�
�쌀�̂���^�C�g�����l�̊�O�ɋ}���ȋ��|���J��L�����v�B
�@����ɁA���̐�ł́A�������p�I�k�قƌ����A�������ʂ���邽�߂�
�����ɗ��ł�����������t�̌��o�ƌ����B
�u���ꂩ��l�́A�l�̖��p�I�k�ق����t�̌��o�ł����Đ��������I
���ɖl�́A�l�̐��_�̍�����_���Ȃ��̂Ǝv���ɂ��������v�B
�@�����Ŕނ́A�͂�����ƁA�u���҂̎��@�v�̊�Ă����Ƃ��ĔF�߁A���̎��H
���琶�������_�̍�����_���Ȃ��̂Ǝv���ɂ��������������q�ϓI�ɒ��߁A��
����܂��߂��ł������ƔF�߂Ă���̂ł���B�����Ă��̌�ɂ�
�u�l�̐��i�͎h�X�����Ȃ����B�l�́A�f�p�ȝR��̂悤�Ȃ��̂̒��ŁA����
���ɕʂ���������v
�Ƃ������傪�����A�u��ԍ������̉́v���}������Ă���B���̎��ɂ��Ă͑O
�ɂ��G�ꂽ���A��͂�A�u�n���̈�G�߁v�̑O�ɏ����ꂽ���̂ł���B���̍�i
�͂����ł͑啝�ɏ���������Ă��邪
�u�����@���旈���A���旈���A
���Y��鎞�旈���v
�Ƃ����Y������鎍��́A��͂��x�J��Ԃ���Ă���B���̐�ł́A
�u�l�͈��L�Y���H�n��������A�����ĉ̐_�ł��鑾�z�ɐg�������o��
���v
�����{�[�����������Y�ꂳ���Ă������̂Ƃ��āA���z������Ȃ���������
�Ƃ͗ǂ��m���Ă��邪�A�����ł���D���ȑ��z�ɐg��a���āA�Ƃ낯�ĂȂ�
�Ȃ��Ă��܂������Ƃ�����]������Ă���B
�����āA���̐�ɂ́A������O�ɐG�ꂽ
�u�����@���肽���@�ς�ꂽ���v
�Ƃ���������܂ށu�T�͖؉A�Łv���}������Ă���B
�@�����A�u���҂̎��@�v�̎��H�ɗ��ł�������ɂ́A��Ăɐ��������Ǝv��
�āA�K���Ȏ����������̂��B
�u���ɁA�����@�K�����A�����@������A�l�͋�F���������������B��
��Ƃ���͍��������A�����Ėl�͎��R�̌��̉����̉ΉԂƂȂ��Đ������B��
�т̂��܂�A�l�͏o������肨�ǂ����A�����ė��ꂽ�\����I�v
�@����]�_�Ƃ̐��ɂ��ƁA��X�����Ă����͐�����ǂ��A�F����s�m��
�����F������݂���͍��������ł���B�Ƃ���A���̎����łɁA�����{�[��
�F���̐^�̎p�������̂����m��Ȃ��B������
�u�ق�@���߂����I
�����H�@�i�����B
����͑��z�ƍ����荇����
�C�v
�Ǝn�܂�L���ȁu�i���v�Ƃ��������}������Ă���B
�@�����A�K���ȏu�Ԃ͒����͑����Ȃ��B���̌�ɂ͂���
�u�l�͉ˋ�̃I�y���Ɛ���ʂĂ��v
�Ƃ���A���̐��s��ɂ�
�u�l�̌��N�͋������ꂽ�B���|���P���Ă����B�l�͉�������������ɗ����A�N
���オ���Ă��A���ɂ��߂����������������B�l�ɂ͉������鎞�����Ă����v
�Ɛ��_�̊�@��ԂɊׂ������Ƃ��q�ׂ��Ă���B�����Ă܂�
�u�����@�G�߂�A�����@���I
�@�����ȐS���ǂ��ɂ��낤���H�v
�Ǝn�܂�A������܂��L���Ȏ����}������Ă���B�����Ē��߂�����̌��t��
����B
�u����͉߂������Ƃ��B�l�͂���ɂ�����������p��S���Ă���v
�@���̔��Ƃ́A�u�n���̈�G�߁v�̖���̏��͂ɏo�Ă����A�����̂悤�ɍK����
�������Ă̐����������{�[����D�����ϔO�I���z�̂��Ƃł���B�ނ͔����
�����߂āA�l�Ԃ̋`�����̂āA���̂�ے肵�A�n���̋ꂵ�݂𖡂�����B����
�����ł́A����͂����߂����������Ƃł���A�ϔO�I���z�Ɉ�������ꂸ
�ɐ����邽�߂ɂ͂ǂ�����Ηǂ������������ƌ����Ă���̂ł���B
�@���ɗ���̂́u�s�\�v�Ƒ肳�ꂽ���ł���B���̎��͎������ǂ����߂Ă�
�����̂���T�ł��������Ƃ̊m�F����n�܂�B
�u�����I�@�l�̏��N����̂��̐����A�ǂ�ȓV��̉��ł��X����������A��
��Ȃ܂łɈ��H��ߐ����A��H�̈�ԗD�ꂽ�҂�薳�~�ŁA�c�����A�F�l��
�����ʂ��Ƃ��ւ�Ƃ��Ă����B���Ƃ��������Ȃ��Ƃ������̂��낤�B�\�\�\
�����āA�l�͍��悤�₭���̂��ƂɋC�t���̂��I�v
�@�����ĉ��䂦�ɁA����Ȍ�T�Ɋׂ����̂��T���Ă����B
�u�l�ɋ͂�����̗������߂��Ă����̂ń����������ɏ����Ė����Ȃ邪
�������l�̋��S�n�̈����́A�l���������m�ɂ��邱�Ƃɏ[����������C�t��
�Ȃ��������Ƃ��琶�܂�Ă��邱�Ƃ�����B�l���ώ��������A���サ���`�A
���ꂽ������M���Ă���Ƃ�����ł͂Ȃ��̂����E�E�E�v
�ƁA���������ςɎx�z����A�i��v���Ƃ����̂͌��Ȃ̂ł��B�l����v��
�Ƃ����ׂ��Ȃ̂ł��B�\�\�\���҂̎莆���j�����̐l�Ԃ������Ă����G�l��
�M�[���\�͂������Ă��܂������サ�����m�ɐ��܂��������Ƃ����Ӗ��̏d
���ɋC�t�����A�����̐l�Ԃ̔\�͂����߂����Ƃ�����]����������ƂɁA��
���̌��������o���i�u�����ǂ�D�v�̍Ō��3�߂ł��łɁA���[���b�p�ւ̋��D
������Ă������Ƃ��v���o���Ă������������j�B�����āA���m�̑ɂɂ����
�̂Ƃ��ē��m�Ɏv�����͂���B
�u�l�́A���m�ɁA�����̂����ĉi���̉b�q�ɖ߂����B�\�\�\�����A����͑e��
�ȑӑĂ̖��ł���炵���I�v
�Ɛ��m�ɐ��܂������҂ɂƂ��ẮA���m�̉b�q�ɖ߂�ȂǂƂ������Ƃ́A��
�ɉ߂��Ȃ����Ƃ��q�ׂ���B�����Đ��s��ł́A
�u�����A�Ȋw�̐錾�ȗ��A�L���X�g���́A�l�Ԃ́A������M�сA���肫������
�Ƃ��Ȃɏؖ����Ă݂��ẮA�����̏ؖ����J��Ԃ���тŖc��オ���Ă�
��B����ȕ��ɂ����������Ȃ��Ƃ������Ƃ̒��ɁA�{���̐ӂߋꂪ�����
�ł͂Ȃ��낤���I�I���Ŕn���n�������ӂߋꂾ�G�l�̐��_�̜f�r�̌����E�E�E
����ȓł����������Ȃ�A���ׂ̈̋ߑ㐢�E���I�v
�ƁA�͂�����ƁA�����̑�]�������s�\�Ȃ̂́A���m�̌�������l�ςɂ��
�Ĉ�Ă��A�͂�D��ꂽ����ł��邱�Ƃ�F�߂Ă���B�������m�ɐ��܂ꂽ
�Ƃ������Ƃ́A�O�q�������q�̈�e�W�ɂ���
�u�����͂��̎���A���̊��̒��ɂ��̂悤�ɐ����ė����Ƃ��������̌��̑S
�Ă����̏h���ł���E�E�E�E�E�E�v
�Ƃ������t�����܂ł��Ȃ��A��̏h���ł���B�h���ɔ��t���Ă��A����
�ď����ڂ͂Ȃ��B�]���āA���̎��̒��ł́A�����{�[�͎����̗��z���������
�̂ł��������Ƃ�F�߁A���܂̌����͗����������A���܂���������E�o����p
�͌����炸�A��]�̌��̎˂��Ȃ���Ԃɂ���B���̎���
�u�S���������悤�ȕs�^���v
�Ƃ�������ŏI���Ă���B
�@���ɗ���̂́u�M���v�Ƃ������ł���B����͎��̂悤�Ɏn�܂�B
�u�l�Ԃ̎d���I����͖l��������ޗ��̒�����Ƃ炵�o���������v
�@����̓����{�[���c���̍�����A�l�Ԃ̎d����ь������Ă������Ƃ��l����
�ƁA�����ׂ��S���̕ω��ł���B�ނ͂P�W�U�Q�N���U�R�N�ɏ����ꂽ��������
�ŌÂ̎U�����u�v�����[�O�v�̒��ŁA���ɂ����q�ׂĂ���B
�u�ǂ����Ą������l�͍l�������̂������������M���V�����e������K��
�̂��낤�H�l�ɂ͕���Ȃ��B���ǂ���Ȃ��̂͗v��Ȃ�����Ȃ����B�l�ɂ�
���ẮA�l�ɔF�߂��邩�ǂ����Ȃ�Ăǂ��ł��ǂ����Ƃ��A�F�߂�ꂽ��
�����̖��ɗ��̂��ˁA���̖��ɂ������͂��Ȃ����A�������낤�H����A��
�����G�F�߂��Ȃ��Ă͒n�ʂ邱�Ƃ��o���Ȃ��Ɛl�͌����G�����l�͒n
�ʂȂ~�����͂Ȃ��G�l�͔N�������҂ɂȂ�̂��v
�@�܂��C�U���o�[�����Ă̌��҂̎莆�̒��ł�
�@�u�������ł����āA���ł��A���ł��A�l�̓X�g���C�L���ł��v
�Əq�ׂĂ���B
�d���Ƃ������t�̎��Ӗ��͑傫���B�d���ɂ��Ƃ������Ƃ͎Љ����
��A���̒��Ő�����ӎu��\���B�]���ă����{�[�́A�c��������Љ�����ۂ�
�Ă����̂ł���B
�@���ꂪ���A���z�������s�\�ł��邱�Ƃ�����A���̌�T��F�߂��ʂ�
�����������o�����Ƃ��o�����A�ޗ��̒�ɂ��鎍�l�̖ڂɁA���܂Ƃ͂����A�l
�Ԃ̐��������w��������]�Ƃ��ĉf��n�߂��̂ł���B
�@�����ނ͂����ɁA���̍l����ے肷��B
�u�\�\�\�l�ɉ����o���邾�낤���H�l�͎d���Ƃ������̂�m���Ă���G�E�E�E�E�E�E
����͒P��������v
�u�d���͖l��遂�ɂ͔�����߂���悤�Ɏv����v
�@�����ĐV�����W�]�����o���Ȃ��̂ŁA�ߋ��̖��ɂ����݂��Ă��邵���Ȃ�
������}����B
�u�l�̐l���͎C��ꂽ�B�����I�S�����܂����Đ����悤�A�̂炭���炻���A
�����@��Ȃ����Ƃ��B�����Ėl�����͉ɂԂ������āA�r�����Ȃ����ƌ�
�z�̐��E���āA�Q���Ȃ���A���E�̊O�ςƓ����Ȃ��琶����̂��낤�v
�@��������ȏo���̖������ɂ����Ă��A�ނ͎���ł��܂����Ƃ͎v��Ȃ��B
�u�����I�����I���A�l�͎��ɔ��R����B�v
�@���͔��R����Ƃ����̂ł��邩��A���R���Ă͖���f�Ƃ��Ǝv����������
�����̂��낤�B�����Ă��̎��́A����ȕ��ɁA��������f���Ƃ������ɐ���
�Ă��ẮA���l�Ƃ��Ă̌ւ�����z�������Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ����₢��
���ŏI���Ă���B
�u�Ŋ��̎���������A�l�́A�E�ɁA���ɒ݂͂������Ă��E�E�E
�ł�����������A�\�\�\�����I�\�\�\���Ƃ�������ȍ��感���i���́A�l��
���ɂƂ��Ď����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����낤���I�v
�@���ɂ���̂́u���v�Ƃ������ł���B���̒��Ƃ����̂́A��ɏo�Ă�������
�u�n���̖�v����������Ɍ}�������ł���B�����ł͔ނ͑��ς�炸�����̌�
�݂̏�Ԃ�Q�������A�V�����������ւ̈�̊�]�����o���n�߂Ă���B
�u�l�ɂ����ẮA�����ׂ��A�h���ɖ������A�䉾���̂悤�ȁA�����̎��Ђ�
�������߂�ׂ��t���������ł͂Ȃ����A�\�\�\�b�܂�߂��Ă����̂��I�l
�͂����Ȃ�߂ɂ���āA�����Ȃ�߂��ɂ���āA���݂̎コ�ɂӂ��킵���g
�ɂȂ��Ă��܂����̂��낤�H�v
�����Ď��l��������\���҂Ƃ��Đ����邱�Ƃւ̒f�O�������B
�u��̋F��ƓV�g�j����₦�ԂȂ��ꂢ�Ă����H���l�ɂȂ��Ă��܂����l��
�́A�ő�������������邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�l�ɂ́A�������p������Ȃ���
���I�v
�@�����A���́A���̂��Ƃ��ނɁA�s�k���ł͂Ȃ��~���������炷�B���̂Ȃ��
�͂���̂ɁA��������ς��邱�Ƃ��l���n�߂邩�炾�B�����Ĕނ͂��������B
�u�����A����ɂ��A�l�́A�l�̒n���Ɖ�������ƐM���Ă���v
�u�����l�����́A���l��R�X���z���āA�V�����d���̒a�����A�V�����b�q���A
�\�N�ƈ��������̑ގU���A���M�̏I������їE��Ō}���ɂ����̂��낤��
�������l�X�ɐ�삯�āI�\�\�\�����l�����́A�n��ɂ�����N���X�}�X����
���ɍs���̂��낤���I�v
�@�����ɂ́A�܂��A������ɓ���邱�Ƃ��o����̂��͕���Ȃ��Ȃ�����A�V
�����d���A�V�����b�q�ɖڂ������n�߂������{�[�̎p������B�����Ă��̎���
�u�V�̉́A�l�X�̕��݁I�z�ꂽ����A�l�����܂��v
�Ƃ����A�l�Ԃ͊F�h���̓z��ł��邱�Ƃ���Ȃ����A���������A
�Q�����ɐ����čs�����ł͂Ȃ����Ƃ����A���܂łɂȂ��m��I�ȌĂт����ŏI
���Ă���B�������̎��A�����{�[�́A���z�ƌ����̂͂��܂ł̏����ڂ̂Ȃ���
�����قƂ�ǏI���Ă���ƌ�����B
�@���ɗ���̂́u�n���̈�G�߁v����߂����鎍�A�u���ʁv�ł���B���̌���
�����w�S�̂ւ̌��ʂȂ̂��A���邢�́u���҂̎��@�v�݂̂ɑ��錍�ʂȂ̂�
�Ƃ������A�����Ă܂��A����Ɋ֘A���āA�u�n���̈�G�߁v�Ɓu�C�����~�i
�V�I���v�͂ǂ��炪��ɏ����ꂽ�̂��Ƃ������A���̓�_�ɂ��Ă͎��ɗl�X
�Ȑ�����ь��������A���݂ł́u���ʁv�́u���҂̎��@�v�ւ̌��ʂł���A
�u�C�����~�i�V�I���v�́u�n���̈�G�߁v�̌�ɏ����ꂽ���̂ł���Ƃ�����
������ʓI�ɂȂ��Ă���A�ׂ����_���͏Ȃ����A���������ł���Ǝv���B
�@���̎��̒��ł́A�����{�[�̐S���ɂ��܂��Ɏc���Ă��鎍�l�Ƃ��Ă̌ւ�ƁA
�����̒��Œn�ɑ������Đ�����̂��l�ԂƂ��Đ��������ł���Ƃ����l����
�̑������`����邪�A����͍ő����������̂ł͂Ȃ��B�����čŌ�͐V���̊�
�]�ŏI��B
�@�`���Ō����̂́A���l�Ƃ��Ă̌ւ�ł���B
�u�����H���I�\�\�\�����A�ǂ����āA�i���̑��z��ɂ��ނ̂��A�l����������
����̔����Ɍg���҂ł����Ă݂�A�\�\�\�G�߂̏�Ɏ��ł���l�X����
�͉�������āv
�@�����ŏH�ƌ����Ă���̂́A����̏��͂ɂ�����
�u�����ďt���l�ɂ����܂����s���̏����^��ŗ����v
�Ƃ�������ɑ���H�ł���B�܂�A�u���҂̎��@�v���ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��s��
�l�܂���������̂��t�ł����āA���ꂩ�琶���Ȃ���ɂ��Ēn�������������
�������āA�����Č}�����H�Ƃ������Ƃł���B�܂����ۃ����{�[���u�n���̈�
�G�߁v���������̂́A�P�W�V�R�N�S������W���ɂ����Ăł��邱�Ƃ́A�͂���
�肵�Ă��邩��A���̍ŏI�͂������ꂽ�W���ɂ́A���������{�[����炵�Ă�
�����܂�̋��k�t�����X�ɂ͂����H�̋C�z��������ꂽ�Ƃ������Ƃ����邾��
���B�����Ď��l�́A����̂��Ƃ��A�G�߂̏�Ɏ��ł���l�X����͉�������āA
���Ȃ���̔����Ɍg���҂ł���ƌւ炩�Ɍ����Ă���B���������āu���҂�
���@�v�����H���Ă������̎v���o�����
�@�@�u�l�͂������Ŏ���ł��������m��Ȃ��̂��E�E�E�����Ƃ���悤�ȑz�����I
�l�͔ߎS������v
�Ɨ��z�Ɏx�z����Ă���������A���|�������ĐU��Ԃ�B�����Ă��̂������
���҂̎���Ɍ������̐��X����邪�A�����͑S�đ��苎��˂Ȃ�Ȃ��ߋ�
�̂��Ƃł���ƌ��ԁB
�u���ܖl�́A��ɁA��тɖ��������߂̖��������ɕ���ꂽ�ʂĂ��Ȃ��l�ӂ�
����B��ǂ̑傫�ȑD���A�l�̓���ŁA���̂��敗�̉��A�F�Ƃ�ǂ�̊���
�h�蓮�����Ă���B�l�͑S�Ă̏j�Ղ��A�S�Ă̏������A�S�Ă̌���n�������B
�l�͐V�����ԁX���A�V�������X���A�V�������̂��A�V������������悤
�Ǝ��݂��B�l�͒����R�I�ȗ͂���ɓ��ꂽ�ƐM�����B�Ƃ��낪���I�l�́A�l
�̑z���͂Ǝv���o�𑒂苎��˂Ȃ�Ȃ��I�|�p�ƂƂ��ẮA�����Ă܂���
���Ƃ��Ă̑f���炵���h�����D��������̂��I�v
�@�@�@�����āA�l�ԂƂ��č݂�ׂ��p��`���A�ߋ��̎����̐����͋�����ǂ��Ă�
���ƒf�߂��A�^���̐��������ďo�����錈�ӂ��q�ׂ�B
�@�u�S�Ă̓�����Ə����ꂽ���p�t�Ƃ��V�g�Ƃ����̂��Ă����l�A���̖l���A�T
�����߂�ׂ��`���ƁA�������߂�ׂ����炴�炵�������Ƌ��ɁA��n�ɕԂ�
���I�S���ɂȂ�̂��I�E�E�E�E�E�E
�@�Ō�ɖl�͉䂪�g�����U�ŗ{���Ă������Ƃ��ӂ낤�B�����čs���̂��v
�ނ͒n������������A�V�炵�������Ɍ������̂ł���B
�u���̂Ȃ�l�͏������ƌ������Ƃ��o���邩�炾�F���a��̉����A�Ɖ�
�R�����鉹���A���L����v���o�������Ȃ����B�����鉘�ꂽ�v���o�͏�
���������v
�@�@�Ƃ͂����u���҂̎��@�v�̍��܂���A�����Ɏ���܂ł̓��͐h�������B�ނ́A
���z�ɓ��B�o���Ȃ����g�̎����ƁA�����܂ł����z��ǂ��A�u���C�̏����v��
�v�̂悤�ɁA���z�̒B����W���鐶�g�̎�����ӂߑ����������l�̎�����
�́A���߂������̋ꂵ����U��Ԃ��Ă��������B
�u���_�̓����͐l�ԋ��̓����Ɠ��l�ɂނ����炵���v
�@�@�����A���̂ނ����炵���������I���A�V���ւ̐S�̏����͐������B��͏o
�����邾���ł���B
�u���������͂܂��O�邾�B�͋��������͂ƌ����̏�Ƃ����ꍞ��ł���̂�
�S�Ď���悤�B�����ċł�������A�R���オ��E�ςŕ������āA�l����
�͌���P�����X�ɓ����čs���̂��v
�@�@�����Ă��̎��́A���x�����́A�܂₩���łȂ��^����߂炦�邱�Ƃ��o���邾
�낤�Ƃ�����]�ŏI���Ă���B
�u�����Ėl�ɂ́A��̍��ƈ�̓��̂̒��ɁA�^�������L���邱�Ƃ�������
�邾�낤�v�B
�@�@�@���̎��������āA�����{�[������̐t�̋O�Ղ����ǂ��ĒԂ����u�n���̈�
�G�߁v�͏I��B�ނ́A�������O�A���q�Ȃǂ́A�����{�[�𐒔q���A���z��
�g����������l�����̂悤�Ɏ���̖���f���Ƃ͂����ɁA��Y�ɑς��Đ���
�i�炦�A���z�ƌ����̑��������z���āA�t�̊�@��E�����̂ł������B
�@�@�@���Ɏ��グ��ׂ����W�́u�C�����~�i�V�I���v�ł���B��ɂ��q�ׂ����A
���̎��W�̑n��N��ɂ��ẮA�u�n���̈�G�߁v�̑O�Ƃ�����ƁA��Ƃ����
�Ƃ����邪�A���݂ł͌�Ƃ��������ʓI�ł���A�l�X�ȗ��R���玄�������v
���̂ŁA���̊ϓ_����A���̎��_�̗���ɉ������`�I�v�f�̔Z������̎���
�����s���Ɏ��グ�A�l�@���Ă݂����B
�@�܂��u�o���v�Ƒ肳�ꂽ���B�Z�����̂Ȃ̂ŁA�S���Ă݂悤
�u�[�������B�����ɂ͂����Ȃ��C�̒��ł��o������B
�[����ɓ��ꂽ�B�X�̌����A����A���z�̉��ł��A���ł��B
�[���m�����B���̒�B�����������A�����Ǝ����I
�o�����B�V��������Ƌ����̒��Łv
�@�@�@���̎��ɂ͐����͗v��܂��B�����ɂ���̂́A�ő����܊��̒��Ŗ��̂݉i��
���Ă���҂̎p�ł͂Ȃ��A�ߋ��ɋ������A��]�������ĐV���������Ɍ�
�������Ƃ��Ă��鎍�l�̎p�ł���B
�@�@�@�u���҂̎��@�v�̕s�\����鎍���������B�܂��u�C�����~�i�V�I���v
�̖`���ɒu���ꂽ�u��^���̌�v�B����́A�m�A�̍^�����v�킹���^���ɂ��
�āA�l�Ԃ����グ���S�Ă̂��̂������ꂽ����̐V�N�Ȑ��E�̕`�ʂ���
�n�܂�B��������͐��s�ŏI���A�����ɐl�Ԃ����̈ȑO�ƕς��ʊ������n
�܂�A�ЂƂ��ѐ��炩�Ȍ����̎p�ɖ߂������E���A�l�Ԃ̊����ɂ���Ēz����
�����̂ɂ���Ď��X�ɉ�����Ă����l���`�����B�l�Ԃ̗͂́A�A���v�X�R��
��ɒn�̕X���ɂ܂ŋy�ԁB
�u╳╳�v�l�̓A���v�X�R���Ƀs�A�m�𐘂��t�����v
�u�����ċɒn�̕X�ƈł̍��ׂ̒��ɑs��ȃz�e�������Ă�ꂽ�v
�@�@�@���l�͂�����x��^�����N���邱�Ƃ�����B
�@�@�u����������A����������A���������̏�ŁA�X���z���āA�A�����A�]����I
�������������V���ƃI���K����A��������ȂƗ���A��������������A�]
����I���������Ɣ߂��݂�A��������A��^���������N�����Ă���v
�@�����^���͓�x�ƋN����Ȃ��B���l�͌��ӂ��o����B������
�@�@�u�����̒ق̒��������������ĂĂ��閂���́A�����Ėl�����ɁA�����͒m��
�Ă��邪�A�l�����͒m��Ȃ����Ƃ�����Ă���悤�Ƃ͂��Ȃ����낤�v
�ƒ��߂�����B����͖��炩�ɁA���l�I�Ȏ��͂���Ă邱�Ƃɂ���āA�F����
�_��ɔ��낤�Ƃ����u���҂̎��@�v�������s�\�ł��邱�Ƃ�F�߂����t�ł�
��B
�@�܂�
�u�ޏ����l�����āA��ɍ��܂����]����������ȂǂƂ������Ƃ����蓾�邾
�낤���H�E�E�E�E�E�E�����������̓����A�h���I�Ȗ��n���̒p�̏�ŁA�l
�����荞�܂���ȂǂƂ������Ƃ����蓾�邾�낤���H�v
�Ƃ��������o���Ŏn�܂�u��Y�v�́A�u�n���̈�G�߁v�Ɠ������ɏ����ꂽ��
�̂Ɛ��肳��Ă��邪�A�啶���ŏ����ꂽ�ޏ��Ƃ������t�Ɏ��ɑ��푽�l�ȉ�
�߂������āi���Ƃ��ẮA���l���̔�]�Ƃ������Ă���悤�ɁA�����{�[�̐l
�Ԍ`�����x�z�����A���i�ŁA���ȉ��l�ς̎�����ł���ނ̕�e���ނ̐S��
����ɐA�������K�͂ƍ̂肽���B���_���͓I�Ɍ����Β�����Ƃ������Ƃɂ�
��̂��낤���A���Ȃ݂ɋK�͂�\�킷�t�����X��norme�͏��������ł���j�A��
�̌�̉��߂̎d���ɂ���đ��̕����̉��߂��قȂ��Ă���̂ŁA���ɓ����
���Ƃ���Ă���B�����A���̉��߂̂悤�ɍ̂�A����́A��͂��ɕ���
���������{�[�́A�ނ����炵�����_�̓����̂��Ƃ������Ă��邱�ƂɂȂ�B��
�̉��߂𗠕t����悤�ɁA���̎��͑S�̂Ƃ��ẮA���z��ǂ������ɔj�ꂽ��
�̒ɂ݂���������̂ł���B�����
�u�����A�l���������ƂȂ����ǂ��q�ɂ��Ă��܂��z���S�͖�����B�킽������
�O�����ɂ䂾�˂����̂����ŗV��ł��Ȃ����ƁB�����Ȃ���A�����Ɗ��m
�Ȃ��ƂɂȂ邾�����ƁB
���肷���C�ƊC�̒��ŁA���̒ɂ݂ɂ̂������܂��̂��G����������
�����Ƒ�C�̒��ō�����A���̂ނ����炵�����˂钾�ق̒��Ś}����
�ӂߋ�ɂ����A�̂������܂��̂��v
�Ƒς���ꂵ�݂̕\���ŏI��B
�@�@�@�������A���̂悤�Ȏ�����ł͂Ȃ��B���ɂ́u���҂̎��@�v�̂��̊Ԃ�
�������S�������̂����邪�A�����͂ǂ���A�����K�����߂�悤�ɁA���҂�
���E���猻�����E�ւ̔������Ȃ����A�Œ��߂������Ă���B
�Ⴆ�u�����v�B�Z�����̂�����S���Ă݂悤�B
�u������������A���ɉ��₩�Ȑl�X�̒��ŁA�ڂ�������悤�ɔ�������l��
�j�ƈ�l�̏��Ƃ��A���O�̖ʑO�ŋ���ł����B�w�݂Ȃ���A���͔ޏ�������
�ɂ������̂ł��I�x
�w���͉��܂ɂȂ肽���̂ł��I�x���͏������Đg��k�킹�Ă����B�j�͊F
�ɁA�V�[�ɂ��āA�Ȃ��I���������ɂ��Č���Ă����B��l�͂Ђ��ƕ���
�������܂܋C���������B
���ۂɁA��l�͉��������B�ƁX�ɐ[�g�F�̖����f����ꂽ�ߑO�̂�������
�[���ƁA�����ē�l�����L�̒�̕��i��ōs�����ߌ�̂����������[��
�Ɓv
���̓�l�Ƃ́A���炭���l�Ǝ��̏��_�ł��낤�B���l�͌��҂ƂȂ邽�߂̎�
�����I���āA���_��߂炦�A�������B����������͒�����[���܂ł���
�����Ȃ��B
�@�܂��u���̌ߑO�v�B����́A�����{�[�̃n�V�b�V�����p�̌��������ꂽ��
�̂ŁA���l�̓n�V�b�V���̌��͂ɂ���ĐS�̕s���a����������A�V�����n��
�ꂽ���̂ƍ��ɑ��ĂȂ��ꂽ���l�I�Ȗ��ɂȂ��Ă����W�߁A�n�V�b
�V�������҂ɂȂ���@�Ƃ��čm�肷��ƌ��B
�u�����₩�ȓ����̖�A���Ƃ����ꂪ�A���O���l�����ɉ��ʂƂ��Čb��ł���
�����̂ɉ߂��Ȃ��ɂ��Ă��A���Ȃ���̂Ȃ̂��I�l�����͂��O���m�肷��I
���@�Ƃ��āv
�����Ă���܂ł́A��i�̒��ōD��Ŏ������A���ꖳ�����̂̏ے��A�u�q��
���v�ƌĂсA�u�n���̈�G�߁v�́u���ʁv�̒��ł�
�u�G�߂̏�Ɏ��ł���l�X���牓������āv
�Ǝ��ԂɎx�z����Ȃ��҂ł��邱�ƂɎ��l�Ƃ��Ă̌ւ�����o���A�܂��u�C��
���~�i�V�I���v�̒��́u���闝���v�ɂł́A�q�ǂ������̌������
�u�l�����̉^����ς��Ă���A�Ђ������������ɂ��Ă���B��n�߂ɂ܂�����
����v
�Əq�ׁA���̗�������ۂ������Ƃ�����]��\�킵�Ă��������{�[���A������
���߂Ď��Ԃɑ��錩����ς���B
����܂ł̃����{�[�̎��Ԃɑ��錩���̓{�[�h���[���̎��u�����Ă�����
���v���v���N����������̂ł������B�{�[�h���[���͗L���Ȏ��A�u�����Ă���
�܂��v�̖`���ł����q�ׂĂ���B
�u��ɐ����Ă��Ȃ���Ȃ�ʁB�S�Ă͂����ɂ���B���ꂪ�B��̖��ł���B
���Ȃ��̌���ł��ӂ��A���Ȃ��̐g��n�Ɍ����Ă����߂����鎞�Ԃ̋��낵
���d�ׂ������Ȃ����߂ɂ́A�₦�ԂȂ������Ă��Ȃ���Ȃ�ʁB
�������ɁH���ɂł��A���ɂł����邢�͔����ɂł��A���Ȃ��̂��D���Ȃ���
�ɁB�����A�����Ă��Ȃ����v
�{�[�h���[�����܂��A���Ԃɂ��Ȃ̕ω��Ǝ�������A���ۂ����������̂�
����B
���������{�[�́A����܂ł͏������C�ł��邱�Ƃ���̑傫�ȉ��l�Ƃ���
�����ɂ�������炸�u���̌ߑO�v�Ŏn�߂Ď��Ԃɂ��ω��A�����ĘV������
�������B
�u�l�����͂��O������A�l�����̔N��̂��ꂼ��ɉh����^���Ă��ꂽ���Ƃ�
�Y��͂��Ȃ��v
�@���������������܂ł���낤�Ƃ���Ȃ�A����܂�����f�����Ȃ��B����
���A�����Ń����{�[�́A����܂ł̏������C�ɖ���̉��l��F�߂�l�������߁A
���������ۂޑ�l�Ƃ��Đ����čs���˂Ȃ�Ȃ��Ƃ����R�����Ȃ���������
����A�N��̂��ꂼ��ɉh�������邱�Ƃ�F�߂��̂ł���B
�@�����āu���̌ߑO�v�Ō��ꂽ�K���ȑ̌����A�薼�������悤�ɁA�ߑO��
�Ԃ��������Ȃ��B
�@���̌����̎��Ԃ̏������A�����Ƃ͂�����\������Ă���̂́u���v�Ƃ���
���ł���B�����
�u�l�͉Ă̏���������v
�Ƃ������t�Ŏn�܂�B�Ă̏��́A�����̎���莆�̒��Ŗ��炩�ɂ���Ă����
���ɁA�����{�[���ł��D�ގ��Ԃł���B�ނ͑S�Ă��܂����肩����߂Ȃ��V�N
�Ȏ��R�̒����A������̑u�₩�ȕ��i�߂Ȃ������ōs���B����Ƌ�F��
��ɏ��_�̎p��������B�����Ŏ��l�́A���_���g�ɒ����Ă��郔�F�[�����ꖇ
�Â������Ă����B���_�͓�����B���l�͒ǂ��B����o��߂��Ƃ���Ŏ��l
�͏��_�ɒǂ����A�܂���d�ɂ��g�ɒ����Ă��郔�F�[�����ƁA���̋���ȑ�
��������߂�B�����ď��Ǝ��l�͋��ɐX�̉����ɓ|���B
�@����͖ܘ_�A�厩�R�̐_��ɔ��낤�Ƃ��������{�[�̖ژ_�����ے���������
�ł���A���҂ƂȂ����ނ͐_����Ă��郔�F�[�������Ȃ��珗�_��
�ǂ������A���ɂ͔ޏ���߂炦�A�����������܂܍K���Ȗ���ɗ�����̂ł�
�邪�A���̌�Ɉ�s��
�u�ڂ��o�߂�ƒ��������v
�Ƃ����ŏI�s������B�܂肱���ł����҂̎����̑̌��͒����͑������A����
�Ɍ����̐��E�Ɉ����߂����̂ł���B
�@�����A�����O�̎��т̒��Ń����{�[�͂��̂��Ƃ�Q���Ă͂��Ȃ��B���
���p�����u���̌ߑO�v�̒���
�u�����₩�ȓ����̖�A���Ƃ����ꂪ�A���O���l�����ɉ��ʂƂ��Čb��ł���
�����̂ɉ߂��Ȃ��ɂ��Ă��v
�Ƃ������悤�ɁA�ނ͂����u���҂̎��@�v�ɂ���Č������̂��^���̕��ł���
�Ƃ͎v���Ă��Ȃ��B����͂����Ƃ��̖��A���ʂł����āA�����̎��Ԃ̑O�ɂ�
�R���������镨�Ȃ̂��B�ނ́A�ŏI�s�ŒW�X�Ƃ��̂��Ƃ��q�ׂ邱�Ƃɂ���āA
�������ő��A�����̎��Ԃ̗���ɋt�炨���Ƃ��Ă��Ȃ����Ƃ������Ă���̂�
����B�����݂̂����Ȃ���̂ł��邱�Ƃ�m�����̂ł���B
�@�Ō�ɁA�����{�[���t�̊�@�������ɂ��ď��z���A��l�Ƃ��Đ����铹
�Ɍ����������𖾔��ɕ�����Ă���u���b�v�Ƃ����������グ�Ă݂悤�B��
���������S���Ă݂�B
�u��l�̉��q���A����܂Œʑ��I�Ȋ��傳�̊����݂̂ɐ�O���Ă������Ƃɕ�
�𗧂ĂĂ����B�ނ͈��̋����ׂ��ϊv��\�����A�ނ���芪���������ɂ�
�ґ�Ƃ��M�S�ŏ���ꂽ���̂��Ǐ]���܂��Ȃ��Ƃ��o����̂ł͂Ȃ�����
�v���Ă����B�ނ́A�^�����A�{���I�ȗ~�]�Ɩ����̎��������������B���ꂪ
�M�S����O��Ă��悤�Ƃ��܂��ƁA�ނ͂����]�̂������B���Ȃ��Ƃ�
�ނ́A�l�ԓI�ɂ͂��Ȃ�D�ꂽ�\�͂������Ă����B
�@�@�ނ�m�����������́A���Ƃ��Ƃ��E���ꂽ�B���̉��̉��Ƃ����r�p�I�邬
�̉��ŁA�������͔ނ��j�������B�ނ́A�V�������ȂLj�l�Ƃ��Ė����Ȃ���
���B�������������͍Ăь��ꂽ�B
�@�@�ނ͎����ɕt���]���҂������݂�ȎE�����A��̌�ŁA���邢�͎�����
��ŁB�������݂�Ȕނɕt���]���ė����B
�@�@�ނ��ґ�ȏb�����̍A��~�����Ċy���B����̋{�a�����コ�����B
�l�X�ɗx�肩�����Ă͂��������ɐ荏�B����������ł��܂��A�Q�W���A
�����̉������A�������b���������݂��Ă����B
�@�@�@�l�͔j��ɐ����s��邱�Ƃ��o����̂��낤���A�c�s���ɂ���Ď�Ԃ邱
�Ƃ��o����̂��낤���I���O�͍R�c�̐����k�炳�Ȃ������B�����N��l�ނ�
�Ӑ}�ɗ͂�݂������Ȃ������B
�@�@�@����[���A�ނ͌ւ炩�ɔn�𑖂点�Ă����B����ƈ�l�́A�M��ɐs����
�@�@�ʂقǁA���t�ɂ��悤�Ƃ��邱�Ƃ����݂���قǔ��������삪�p���������B
���̕��e�A���̕�������͑��l�ŕ��G�Ȉ��̖��A�����₷��A�ς���
�����炠��K���̖��ɂ��ݏo�Ă����B���q�Ɛ���́A���炭�{���I�Ȍ�
�N�̒��ŎE���������B���ꂪ�ǂ����Ď��Ȃ��ɂ����悤���H�]���Ĕނ��
���Ɏ��B
�@�@�������q�́A�����̋{�a�ŁA�ʏ�̔N��ł݂܂������B���q�͐��삾�����B
����͉��q�������B
�@�@��X�̗~�]�ɂ͍I�݂ȉ��y�������Ă���v
�@������܂��A���푽�l�ȉ��߂�i�ł���B���������{�[�̍��ܑ̌�
�ƁA��������̑h���\�킵�Ă���ƍl����A���߂͔�r�I�e�Ղł��낤�B
�@���q�͂܂��A���鎞�A���������ԂŌ���������Ȃ���̂̊����̂��߂ɐ�
�O���Ă������ƂɋC�t���A�{����o����B�����āA�ϔO�I�Ȃ��̂̌���������
�����̎�҂����Ɠ��l�ɁA�����Ɛ^���͈قȂ�ƍl���A�^�����������A�{���I
�ȗ~�]�Ɩ����̎����������Ƃ�����]������A���̗��z��B�����邽�߂ɁA��
���Ɏ�������芪���Ă���S�Ă̂��̂�r�����悤�Ƃ���B
�@���������Ƃ������̂́A���̐��ɐ����Ă������́A������r�����悤�Ɨ�
��s�����Ă��A�r���������̂ł͂Ȃ��B�ނ��₢�𗁂т������������A
�y���ݎ��̌�ɖ���D�����]�b�������A�A��~�������������b�������A����
�ɍĂюp�������A�ނɕt���Z���B���q�̖ژ_���𗝉��o���Ȃ��l�������́A��
�����Ȃ�����͂����Ȃ��B���q�͌ǓƂł���A��������l�ŎE�C���J���
���B
�@����Ȃ�����A���q�͈�l�̐���Əo��B���̐��삪�����Ӗ����Ă����
���ɂ��ẮA�܂��������������Ƃ���ł��邪�A���́u���q�͐��삾�����B
����͉��q�������v�Ƃ�������ɒ��ڂ��āA���l���̔�]�Ƃ������Ă���悤
�ɁA����͉��q�̕��g�A������u�n���̈�G�߁v�́u���C�̏����v�ɏo�Ă���
�u�n���̕v�v�̂悤�ɁA�ϔO�I�ȗ��z�ɖ������Ă����ǂ����߂镪�g�ł�
��ƍ̂肽���B���q�Ɛ���́A�{���I�Ȍ��N�̒��ŎE���������B�����A�{���I
�Ȍ��N�Ƃ͉��ł��낤���H����͂܂��ɁA���N�Ȑ��_�ɂƂ��Ă͓�����O�̂�
�Ƃł��錻���̍m��A���̎�e�̂��Ƃł͂Ȃ����낤���H������ϊv���悤��
����̂͗ǂ��B����͎��Ƃ��ĕK�v�Ȃ��Ƃł���B�������̖ڕW���n�ɑ�����
�������̂łȂ���A���ǂ͌�����ے肷�邱�ƂɂȂ�A�ϊv�͊G�ɂȂ�A
�s�k���邾���ł���B���q�����}�ɋ��߂��̂́A������ے肷��Ɏ���A����
�Εs���S�ȗ��z��B�����邱�Ƃ������B���ꂪ����Əo����āA�������m�肷
��{���I�Ȍ��N�̒��ŎE���������B�]���Ď��̂́A�����₷���������
����̕��ł���A���q�͐q��̔N��ŁA�����̋{�a�ł݂܂������B
�@�܂�A���q�͗��z��ǂ����߂镪�g���E�����Ƃɂ���āA�����̎����ɗ�
���Ԃ�A�V�N�܂Ő����i�炦���̂ł���B�l�Ԃɂ͏h���I�ɒB���s�\�ȗ��z
���̂Ă邱�Ƃɂ���āA���ʂ̐l�ԂƂ��āA���̗���̒��Ő����A�����ĘV��
�Ď��̂ł���B
�@�N�w�҂ł��茴�����O�����E���������ꍂ�̋����ł������X�L���́A������
�u��\�̃G�`���[�h�v�Ɋ������A�u��������ҁv�̒��Ŏ��̂悤�ɏq��
����B
�u�ϔO�����ꂽ���Ȃɐ�����s�����A������m�肵�A�т����Ƃ��āA�ߑ��
���U�Ǝ��ȋ\�ԂƂ����������B�E�E�E�E�E�E�����ϔO�������Ƃ̌��ɑς�
�Ȃ���A���ꂪ�����ɖ����ł���A����������A�����I�ł����Ă��̂Ă�
����Ȃ�ʁB����͂���Ӗ��Ŏ��Ȃ��̂āA���Ȃ�ے肷�邱�Ƃł����āA
�ُ�Ȑ��_�ْ̋��Ɗo��Ƃ�K�v�Ƃ��邱�Ƃł���v
�@�����{�[�́A���̐��̂��̂Ȃ�ʔ������̐�����E�����Ƃɂ���āA�܂���
���̍�Ƃ��s���A�ނ𖣗����Ă����ϔO���̂Ă��̂ł���B�������Ĕނ͍���
�����z���A�������g�̌����Ǝ��Ԃ̗���Ƃ�����Đ��������邱�Ƃ�I
�B�]���āA���̎��͖��炩�ɑh��̉S�ł���B
�@�ȏ�q�ׂĂ����悤�ɁA�����{�[�͂P�V�ɂ��Ēʏ�̐l�Ԃɂ͎v�����y��
�Ȃ���]������A���̎��H�ɗ�����܂��A��x�͂���̂ɐ�]�̂ǂ���
�˂����Ƃ��ꂽ���A�u�n���̈�G�߁v�������Ȃ��炻�����甇���オ��A�u�C
�����~�i�V�I���v�̐��҂̎��̒��ŁA�t�̊�@�����z���ĐV�����A��n��
���݂��߂������Ɍ��������Ƃ������ӂ������Ă���B
�@����Ȃ̂ɉ��́A�����{�[�ɌX�|�����҂����̊ԂɁA����̖���f�҂�
�o��̂ł��낤���H�O�q�������q�����Ŏ��E���������A�ޏ��Ɠ����Q�n��
�ؑ����Y�Ƃ������l�́A�ޏ��̂��Ƃ��u�������{�[�v�ƕ]�����Ƃ����B���̂�
�낤�H���������������O�������{�[���u�j�̒��̒j�v�Ə̂��Ď��B���̂�
�낤�H���̃����{�[�ɂ��̂悤�ȁA���z�ɐg��������l�ԂƂ���������C���[
�W���o���Ă��܂����̂��낤�H
�@���w�Ɖ����A�A�t���J�ɓn���Ă���̃����{�[�ɂ��Ă��������Ƃ���
����B�l�ԋ��̓����Ɠ��l�ɂނ����炵�����_�̓����ɔs��āA������r�Ƃ�
�������l�̊ɖ��Ȏ��E�s�̂悤�ȃC���[�W������Ă���l�������B�������ۂ́A
�ނ͂����Ŗf�Ց㗝�X�̏]�ƈ��ƂȂ�A���܂�Ďn�߂Ē�E�ɂ��B�i�u�n��
�̈�G�߁v�́u�M���v�̏͂��v���o���Ă������������j�B�����ĂR�V�ō���
��ɂ���ĒZ�����U���I����܂ŁA���n�̌��t���قƂ�NJ��S�ɏK�����A�댯
�����̂Ƃ��������N�_�ɂ������̐擪�ɗ����āA�R�[�q�[�A�ۉ�A��v�A�l
���A����Ȃǂ̔��荞�݂ɔM�S�ɖz�����A���̖T�烈�[���b�p�l�����̉��n��
�T�����āA���ʂ��t�����X�̒n���w����ɔ��\����������āA�ʊ��ɍs������
����B
�܂��Ƒ��ւ̎莆�ł́A���w�A�H�w�A�V���w�A�d�C�A�C�ۊw�A��C���H�w�A
�@�B�H�w�A���͊w�A�z���w�ȂǂɊւ���{�𑗂��Ă����悤���݁A�����͒�
�ߓ��ɂ����Đ����@�B�S�ʂ̔̔��Ɍg��肽���Ƃ�����]��\�����Ă���B��
��ɂ͌������Ēj�̎q���������A�o�������̋�������������Ƃ�������
����B
�@�����̐��͓I������������ɓ��ꂽ�s�����A�������Ƒ��Ɉ��Ăđ�����
�莆�̒��ŏq�ׂĂ���u�l�͐�ɐ��������݂܂���v�Ƃ������t�Əd�˕���
�Ă݂�ƁA�����ɂ͌����āA���܊��̒��Ő����Ă���҂̃f�J�_���X���Ȃ��
�������Ȃ��B�܂��b���ŁA�������C��̉��ł̗��̊Ԃɂ��A�x���̎��ɂ́A
�����̉��ɐl�X���W�߂ėz�C�Ȃ�����ׂ�ŏ킹��������Ă����Ƃ����B
�ނ͖{���ɑ�n�ɐ�����҂ƂȂ�A�����ňȑO�Ƃ͈Ⴄ�����₩�Ȗ��������A
���悭�����邽�߂̓w�͂𑱂����̂������B
�@�@�@
�@���̓����{�[��������S�Ă̎�҂����Ɍ��������B�����{�[�́A�t�̑�
���Ȗ����j�ꂽ����A
�u�������߂�ׂ����炴�炵�������Ƌ��Ɂv�A
�u�R���オ��E�ςŕ������āv
�����������̂��ƁB�����ă����{�[�ɂ��Ԃ��Ȃ�A�����܂ł��Ԃ�ė~����
�ƁB
�@���̓A�t���J�ł̃����{�[�̐����ɂ��Ă̌��������������o�ł���Ă���B
�A�t���J����̏��Ȃ̑S�������B�����ɏo�Ă��郉���{�[���́A�ߋ���U��
�������A�E�Ƃ������A�������u����Ă���̒��ŁA�J���}�킸�͂�s����
�p�ł���B
�@�����A���̂悤�Ȏp�����炩�ɂȂ������݂ł��A�g�l���𓊂��o���Ȃ�����
�����{�[�h���̒蒅�x�͍����Ȃ��B�]���Ď��́A�O���ł͂ǂ��ł��邩�͒m��
�Ȃ����A���Ȃ��Ƃ����{�ł́A���̌���������{�[�����蒅���Ă��܂����̂�
���l����Ƌ��ɁA�����{�[�͍Ō�܂Ő�����w�͂������̂��Ǝ�҂����ɓ`��
�邱�Ƃ�����̉ۑ�Ƃ��Ă��������B�@�@�@�@
�@�@�@
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��176�|0024
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{��@�N�q
�@
�u���O���炱�̐��M������ꂽ�l�͍ēx�u���O�ɖ߂�܂��B
���L���N���b�N�����������B
http://blogs.yahoo.co.jp/mlouve226/1505666.html
�@
�ڎ����@�@�@�����u�c���v�O�҂ցA�@�@��҂ց@
�@�@
�@�@
�@�@
�@�@
�@�@�@
�@
�@�@
�@